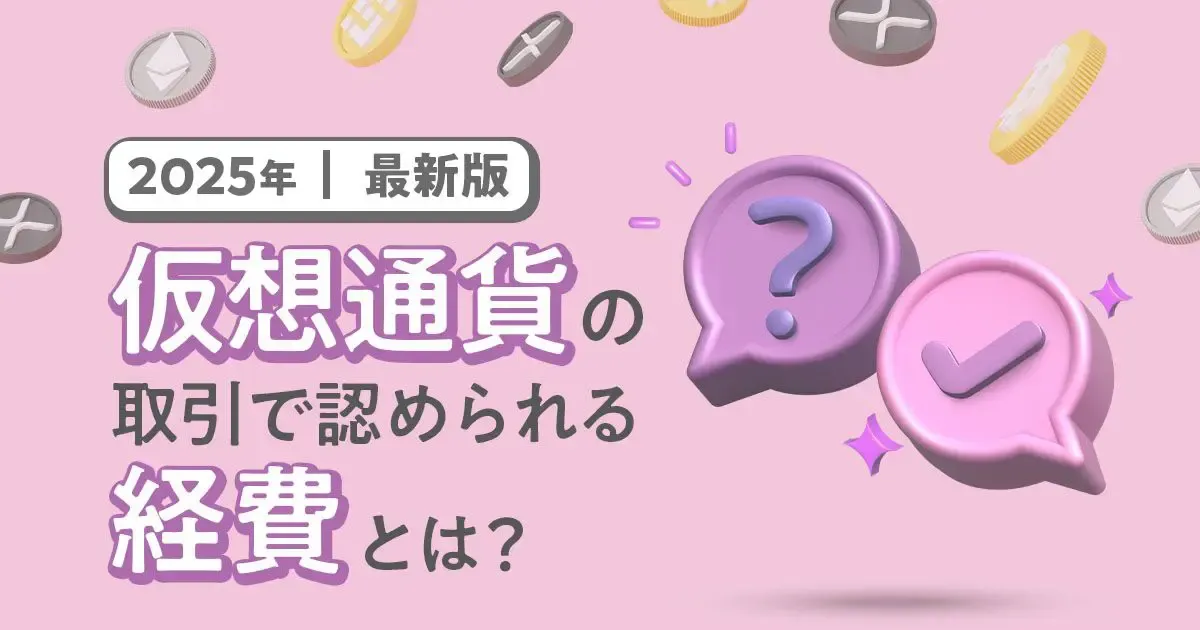
仮想通貨取引で利益を得た際、収入から必要経費を引いた「所得」が一定額以上であれば、確定申告が必要になります。これは、年末調整をしているサラリーマンであっても同様で、確定申告を失念、また怠ってしまうと、最大14.6%と高金利な延滞税が発生してしまいます。
一方、確定申告にて経費計上をうまく利用して課税対象となる所得の額面を抑えれば、支払うべき所得税・住民税を軽減できます。しかし、仮想通貨取引において経費として認められる費用が分からない方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、仮想通貨取引で経費として認められる可能性が高い費用や、所得区分による経費の種類について解説します。仮想通貨取引で得た所得に対して、節税対策をしたい方はぜひ参考にしてみてください。
目次 |
仮想通貨(暗号資産)の確定申告と経費の基本
仮想通貨の経費について考えるにあたり、まずは「所得」とは何かについて整理しておきましょう。
収入から経費を引いたのが「所得」
「所得」とは、収入からその収入を得るために要した経費を差し引いて残った利益のことを指します。そして、所得税の課税は「所得」から基礎控除などの各種控除を引かれた後に残る「課税所得金額」に対して行われます。
所得税は累進課税と呼ばれる仕組みによって、所得が多いほど税率が高くなるように出来ています。
その税率は5%〜最大45%にも達するため、約10%の住民税も併せると最大で所得の半分以上が税金になる場合もあります。
税金を出来る限り安く抑えるためには、経費を適切かつ賢く計上していくことが大切です。経費計上は、シンプルかつ非常に効果的な節税方法なのです。
確定申告や税金計算についての詳細は、こちらの記事でも解説しています。
所得の基本的な計算方法
仮想通貨(暗号資産)取引における所得の基本的な計算式は次の通りです。
所得の計算式
収入(売却金額) - 経費(取得金額 + 手数料等) = 所得(利益)
この計算式は、単純な売買取引だけでなく課税対象となるさまざまな取引に適用できます。
課税対象となる取引
● 仮想通貨を売却(譲渡)した際の利益
● 仮想通貨で商品を購入した際の差額
● 仮想通貨を交換した際の差額
● マイニング・ステーキング・レンディングで取得した仮想通貨
注意点として、取得金額は平均単価に基づいて算出する必要があります。平均単価には「総平均法」と「移動平均法」という2つの計算方法があり、どちらかの計算方法を選択して所得を算出します。
総平均法と移動平均法の詳細や、より税額が低くなる計算方法を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
全額を仮想通貨取引の経費に計上できる可能性が高いもの
経費に計上できる可能性が高いものについて、国税庁の資料「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」に沿って見ていきましょう。
取引手数料・送金手数料
国税庁の資料では必要経費の例示として「売却の際に支払った手数料」が明示されています。
これは取引所に支払う取引手数料や、売却のために仮想通貨(暗号資産)を送金する際の送金手数料(ガス代など)が含まれるものと考えられます。
これらの手数料は日本円建てではなく仮想通貨(暗号資産)建てで徴収されるケースが一般的です。
税務上の経費計算は日本円で行いますので、経費として計上する場合は手数料を支払った時点における日本円換算額をしっかりと記録しておく必要があるでしょう。
仮想通貨(暗号資産)の取得価額
仮想通貨(暗号資産)を売却する際、「その暗号資産の譲渡原価」も必要経費となることも、国税庁の資料で明示されています。
譲渡原価とは、その仮想通貨(暗号資産)を取得(購入)するためにかかった費用のことです。
例えば、1,000万円で購入したBTCを売却する場合はこの1,000万円がそのまま経費として認められ、売却額から1,000万円(及び手数料等)を差し引いて残った額が利益になります。
なお、譲渡原価は平均単価を用いて計算するため、仮想通貨(暗号資産)を複数回取得している場合は譲渡原価の計算が複雑になる点に注意しましょう。
専用のPC・スマホ・周辺機器
仮想通貨(暗号資産)の売却取引には、PCやスマホ、各種周辺機器、そしてインターネット回線などが必要になります。
国税庁の資料では、こうした機器の購入費用について「暗号資産の売却のために直接必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に参入することができます」と記載されており、経費に計上できる可能性が示されています。
ただし、実際に費用の全額を経費計上するには、これらの機器が仮想通貨(暗号資産)取引専用の機材であることを証明できるようにしておく必要があるでしょう。
関連書籍やセミナー費用
仮想通貨(暗号資産)取引に関する関連書籍の購入費用や、セミナー類の参加費用についても、経費に計上できる可能性があります。
本稿で参照している国税庁の資料ではこれらの費用に関する直接的な言及はありませんが、所得税法上の必要経費の原則として、その所得を得るために直接必要な支出は経費として認められるとされているためです。
従って、関連書籍購入やセミナー参加の費用を経費計上する場合は、その内容が仮想通貨(暗号資産)取引に「直接必要」であったことを説明できる必要があるでしょう。
金額の一部を仮想通貨取引の経費に計上できる可能性が高いもの
かかった費用の全額ではないものの、一部を経費として計上できるものもあります。
それぞれ見ていきましょう。
自宅兼事務所の家賃・光熱費
自宅を事務所として仮想通貨(暗号資産)取引を行っている場合、家賃や光熱費の一部を経費に計上できる可能性があります。
ただし、実際に仮想通貨(暗号資産)取引に直接関係している部分がどの程度を占めるのか客観的に説明できる必要があり、費用全体のうちその割合の分だけ経費を計上する形になります。
これは一般的に按分計算と呼びます。
例えば、自宅兼事務所の中に仮想通貨(暗号資産)取引専用のスペースを設けている場合は面積で按分割合を計算する方法があるほか、消費電力や作業時間を測定することで電気代を按分する方法も考えられるでしょう。
通信費やツール利用料
インターネット回線などの通信費や各種ツールの利用料なども、仮想通貨(暗号資産)取引専用でない場合は按分計算が必要です。
インターネット回線の場合、一日のうち仮想通貨(暗号資産)取引だけに用いる時間が何時間あるかによって割り出す方法が考えられます。
例えば毎日2時間、仮想通貨(暗号資産)取引を行っている場合は、インターネット回線利用料の1/12を経費に計上できる可能性があります。
また、確定申告に用いる会計ツール利用料なども、仮想通貨(暗号資産)取引以外の所得を含む場合は按分して経費計上できる可能性があるでしょう。
高額なパソコンの減価償却
たとえ仮想通貨(暗号資産)取引に必要な機材であったとしても、高額な場合はそのまま全額を経費に計上することはできません。
10万円を超える資産は減価償却の対象となり、耐用年数に応じて数年に分割して経費計上しなければならないためです。
パソコンの場合、税務上の耐用年数は4年とされています。
例えば12万円のパソコンを購入し、一般的に多く用いられる「定額法」で減価償却する場合、その年の経費としては1/4にあたる3万円までしか計上できません。そして、翌年以降も償却が終わるまで3万円ずつ経費に計上されていくことになります。
経費にできないもの
次のように、仮想通貨(暗号資産)取引に直接の必要性がないものは経費として計上できません。
私的な交際費や旅行代
当然のことながら、プライベート目的の交際費や旅行代は経費として計上できません。
たとえ仮想通貨(暗号資産)取引の投資仲間との懇親等を目的としたものであっても、取引に直接必要な支出であるとは認められにくいためです。
研修旅行の場合は費用の一部が経費として認められる可能性もありますが、その場合も仮想通貨(暗号資産)取引に直接必要な内容の研修が行われたことを裏付ける写真や資料などを残しておく必要があるでしょう。
情報交換を目的とした飲食費
取引に関する情報交換を理由にした飲食費も、原則として経費にはなりません。
単なる懇談や雑談と客観的な区別がつきにくく、取引に必要不可欠とまでは評価されにくいためです。
飲食の場で仮想通貨(暗号資産)取引に関連する情報交換を行っていたとしても、安易に経費計上すると、税務署から否認されてしまうリスクが高い点に注意が必要です。
納税者の属性(サラリーマンや個人事業主)によって変わる経費の適用範囲
これまで経費計上できる可能性のある項目について解説してきましたが、仮想通貨の経費計上の範囲は納税者の属性によっても違いがあります。
個人事業主が仮想通貨取引を「事業」として行った場合、その所得は「事業所得」に分類されます。
この場合、「仮想通貨の売却などに際し直接要した費用の額」や「仮想通貨取引で発生した損失」に加えて、業務全般で生じた一般管理費などの費用も経費に計上できるため、経費計上の範囲が大幅に広がるのです。
例えば事業用に借りた事務所の家賃や光熱費なども経費の対象となりますし、従業員として家族を雇用している場合は、その家族への給与も経費計上可能でしょう。
一方でサラリーマンが仮想通貨取引を副業として行った場合の所得は原則として「雑所得」に分類されるため、上記のような経費は計上できません。なお、仮想通貨取引が事業として認められるためには一定のハードルもありますので注意が必要です。詳しくはページ下部の関連記事でも解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
ここでご紹介した内容はあくまでも一般的な判断条件であり、実際に事業所得として認められるかどうかはケースバイケースとなります。誤った申告を行った場合、 税務調査に入られた時に追加徴税を課せられる可能性があります。
複雑な確定申告を行う際は、事前に税務署の相談窓口や税理士事務所に相談することをおすすめします。
経費計上とあわせて活用したい所得控除
課税所得を圧縮し、税金を減らすには所得控除の活用も有効な手段です。代表的なものについて見ていきましょう。
生命保険料控除
生命保険料控除は、その年に支払った生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などに応じて所得から一定額を差し引ける制度です。
控除額は最大で年間12万円まで適用可能で、課税所得を減らすことで所得税・住民税の負担を軽減できます。
特に個人年金保険料は、長期的に積み立てることで将来の受取額につながるため、節税効果と資産形成を同時に期待できる点が特徴です。
医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超過分(最大200万円)を所得から差し引ける制度です。
本人だけでなく生計を一にする家族の医療費も対象となり、診療費や薬代、通院のための公共交通機関の利用料などが含まれます。
領収書や明細書を準備し、確定申告で申告することにより、所得税・住民税の軽減効果が得られます。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、個人事業主や中小企業の経営者などが共済制度へ掛金を支払った場合に、その全額を所得控除できる制度です。
将来の廃業や退職に備えた資金を積み立てつつ、支払額をそのまま課税所得から差し引けるため、高い節税効果があります。
ただし、小規模企業共済は個人事業主や経営者向けの制度であり、仮想通貨(暗号資産)の利益を雑所得として申告している会社員など給与所得者は加入できません。
まとめ
仮想通貨取引で利益を得た場合、額面によっては確定申告が必要です。
その際、経費を上手に利用すれば、所得税や住民税を節税できます。
しかし、仮想通貨で得た所得・譲渡価額・手数料を考慮した譲渡原価の計算は複雑です。さらに複数の取引所で取引をした場合には、すべての取引を合算して損益計算を行い、実現損益を算出する必要があります。
仮想通貨の損益計算ツールクリプタクトを活用すれば、取引所のアカウントページからダウンロードできる、取引履歴や送金履歴をアップロードするだけで、取引手数料や送金手数料も加味した損益計算を自動で行うことができ、確定申告に必要な所得計算の簡略化が可能です。
※送金手数料を損益算入する場合は、設定をオンに変更する必要があります。
日々アップデートされる税制基準に基づき、正確かつ簡単に確定申告を済ませたいとお考えの方は、一度無料のFreeプランに登録してみてはいかがでしょうか。



